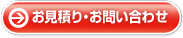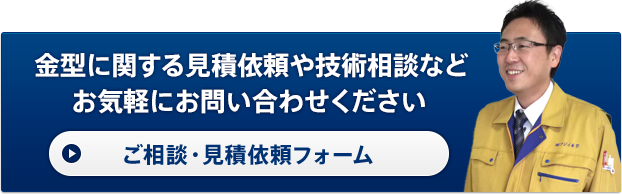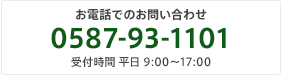1976年 - 1980年
創業前
フジイ金型の文化の最重要キーワードである「分業」。これを理解するために、創業者藤井祥三(現会長)の最初の就職先であった本田技研工業(ホンダ)からルーツをたどっていく。
1960年代はモータリゼーション(自動車の社会的普及)の始まりだった。当時の藤井祥三少年も世の趨勢(すうせい)にもれず、クルマで飯を食っていくつもりだった。中学卒業後、自動車工訓練所に入り整備士の資格を取得、1962(昭和37)年にホンダに入社した。
ホンダは、自動車のエンジンを駆動させるオーバーヘッドカムシャウトを開発、この年の9月に鈴鹿サーキットを完成させている。入社後間もなく配属された鈴鹿工場には、約3000人の従業員がいた。社内改善提案活動をすれば、1グループあたり数件を競って提出してくるといった具合で、伸び盛りの社内は活気に満ちていた。
入社してすぐの仕事は、スーパーカブ(バイク)の部品取り付けの仕事だった。部品を数個取り上げる。それぞれの箇所に置き、締める。ひとつの作業が2,30秒だった。だが、それを繰り返すうち、無造作に部品を取り上げても部品の数、置くタイミング、締める力加減が寸分たがわず均一になってきた。同じ仕事を1日何回も繰り返していくと、動作が体にしみ込み、誰にでも難なくこなせるようになる。職人の原点である。
同時に、作業が細分化され単純になると、すぐに習熟度が上がる。これにより各部品の不良率は下がり、ひいては全体の品質安定につながる。かつ、仕上がりも早い。つまり「分業」とは職人を育てるため、より良い品を効率的に作るために欠かせない手法であることを学んだ。
他にホンダから学んだことに、「モノづくりへの執着」がある。鈴鹿工場勤務時代、創業者で代表取締約社長だった本田宗一郎氏が2度ほど視察に来た。それだけで工場の雰囲気がピリッと締まる。社長自ら現場にやってきて、仕上がりをチェックする。一度など、工員にハンマーをぶつけんばかりに叱りつけている場面を目撃した。その執念に圧倒された。モノづくりには終わりがない。安易に妥協をしてはいけないのだと悟った。
こうして現場での仕事に携わるかたわら、ホンダではいろいろな経験をした。出荷後に判明したバイクのエンジン不具合の修理を、40度近い暑さの船底で行なったこともある。またスーパーカブが岐阜県警で白バイとして採用されたとき、運転指導を担当し感謝された。貴重な体験だった。
ただ、入社10年目近くになり、なんとなく社内での今後が見えてくるあたりから、このまま会社で働き続けることがいいのだろうかと思い始めた。何より、紙一枚でどこに飛ばされるかわからないサラリーマンという立場に疑問を感じてきた。周囲からは、辞めて独立していく人もポツリポツリと現れてきた。将来の選択肢を広げて考え始めた。車の販売店と付き合いがあったことから、一時は車のセールスも独立後の仕事の選択肢の一つとした。しかし、「作っていくら」というシンプルなモノづくりの世界の方が、自分には合っているような気がした。
こうして将来について迷っているとき、ホンダを辞めた先輩が設立した会社で、金型と出会った。
約1カ月で製作されたその金型は300万円だった。当時の初任給が12、3万円だったことを考えると、いかに高額であるかがわかる。これはもうかる、今後仕事として金型作りを手掛けてみようと決意した。
1971(昭和46)年、ホンダを辞め、名古屋市にあったその会社に入社した。そこで1976(昭和51)年の独立まで、他の会社も経ながらプラスチックからダイカストまでさまざまな金型作りを経験し、ノウハウを体得した。
独立にあたっては名古屋市を離れ、心機一転、江南市で開業することにした。名古屋にいると、どうしてもそれまでのつてをたよってしまうからである。開業先を探しているとき、江南市で空き工場となっている旧紡績工場を見つけた。愛知県から岐阜県にかけての地域は、明治以降紡績工業で栄えたため、こうした工場や工場跡地が多く見られた。
工場の中には8社ほどが入居していた。そこにベニヤ板で間仕切りをした、20平米ぐらいのスペースで金型作りをスタートした。汎用フライス加工機、ラジアルボール盤などの機械を購入した。1976年3月、藤井金型の始まりだった。
金型業界の歴史
金型の歴史は古く、今から4500年以上前にさかのぼる。有史以降、金型を使って作られた製品のうち、もっとも有名なのは貨幣であろう。現存する最古の貨幣は紀元前550年のリディア王国(現トルコ共和国)と言われている。このように金型は、同じ形・大きさのものを、大量に、早く作るために必要不可欠なものであった。
金型が産業として飛躍的に発展したのは、工業製品の大量生産が本格的に始まった20世紀以降である。均一・同質かつ精密さを求められる部品を大量に供給する上で、金型はなくてはならないものとなった。マザーツール、いわばモノづくりの陰の主役であり、アメリカ、ドイツが先進国とされた。アメリカの自動車会社であるフォード社が、手作りによる高級品だった自動車を一般大衆に普及させることができたのは、金型のおかげである。
 卓上ボール盤 アメリカ 1808年
卓上ボール盤 アメリカ 1808年しかし70年代を境に、日本の金型業界の競争力は米国を抜き、世界のトップレベルに躍り出る。その理由は「金型は右手にコンピュータ、左手にヤスリである。アメリカの金型産業はヤスリを軽視し、ドイツの金型産業はコンピュータを軽視して衰退していった(日本金型工業会 元副会長細川氏)」からだと言われている。
日本の金型産業の黎明期(れいめいき)は、高度経済成長時期(1954〜73年)に重なる。この時期成立したさまざまな「金型屋」が会社として発展していくプロセスを検証したとき、2つのタイプに分類される。大多数を占めるのが、いろいろなものを作っているうちに金型業に転じたいわゆる「町工場型」である。他方が、メーカーの一部門が高い技術を有したまま独立した「独立型」だ。いずれも、戦後日本の基幹産業となった自動車産業や家電産業とともに発達した。
金型の形状は、現在のものに比べると総じてごくシンプルであった。しかし品質は安定せず、納品後に不具合が見つかることもしばしばだった。最大の理由は、熟練工らの技量を要する部分が大きかったからである。
初期段階では、旋盤、ボール盤といったいわゆる汎用工作機械の使用が中心で、手作業に多くを負わなければならなかった。フライス盤や平面研削盤など、金型加工で専用的に使用される機械が、業界の多数を占める小規模事業所に普及したのは60年代である。現在の主力であるNC工作機械や放電加工機の登場は、70年代も半ば過ぎてからであった。
 ドラフター<参考写真>
ドラフター<参考写真>金型は、基本的には単品注文生産品である。設計図も注文先から渡された完成品の図面を見ながら、ドラフターを使って職人が金型の図面を逐一作成していた。自動車のボンネットのような複雑な形状ですら設計図がなく、現物を見ながら鋸で切り出してヤスリで仕上げたという記録も残っている。結果、金型の品質は、職人のウデによって大きく左右された。
この特殊な専門性は、当時の職人に「作ってやってる」という態度を生んだ。納期が大幅に遅れるなどは日常茶飯事で、客先が督促すると「まだできん」のひと言で終わらせることも多かったという。技術に自信のある職人は「流れ職人」として職場を渡り歩いていた。いかに質の高い職人を確保するかが、多くの金型屋にとっての課題だった。
このように、70年代前半、藤井祥三が金型修行をはじめたころ、「外形加工(面削り、分割面加工)」「型彫り」「仕上げ」といった3段階のプロセスを、1人あるいは1つのチームの職人で、一貫して作り上げていたのが日本の業界の現状だった。しかしちょうど独立した1976年頃より、金型はユーザーの要求に応え、次第に複雑化・高度化する。それにともない、製造工程の分担や設計図・工作機械の精度向上が、業界に求められてきたのだった。
分業をめざす
 汎用フライス盤 (日本 製造年不明)
汎用フライス盤 (日本 製造年不明)藤井金型として独立後しばらくは、仕事も雇用も安定していなかった。そのなかでも藤井祥三は熟練工に頼ることなく、新人に一から金型作りのノウハウを伝え、製造に当たりたいと考えていた。しかし実際には、流れ職人を合わせて2,3人の職場は常に人が入れ替わっていた。
その頃最も苦労していたのは、初期設備投資などに対する、多額の返済への資金繰りである。これに奔走するかたわら、朝の6時から夜の0時まで働いた。夜の11 時まで自分の仕事をし、そこから他の金型会社に夜中の2時まで手伝っていたこともある。体力の限界までがんばっていた。
主力はプラスチック金型の製造で、全生産の7割程度を占めていた。仕事の大半は近所にあった金型会社の下請けとして、そこでこなしきれない業務を引き受け、納品していた。一時期はパチンコの受け皿製作を一手に請け負っていた。パチンコ皿なら藤井に頼めと言われたほど評判が高かったらしい。その他はガス管関係受注から伸び始めたアルミ、あとはプレス加工の仕事などがあった。
受注した業務に追われてはいたが、1977(昭和52)年に榊間英志が入社してきた頃から、白紙の状態から少しずつ現場で仕事を覚えてもらうやり方を取れるようになった。それを可能にしたのが、創業当初からのアイデア「分業」である。
金型では、ひとつの製造過程を覚えるのに3カ月、ひととおり金型のことが分かるのは3年はかかると言われている。全部の過程を任せるのではなく、まず旋盤なら旋盤など限られたプロセスに習熟し、次の工程に責任を持ってつなぐようにした。
生産高は、月に400万円程度、約140万の金型を月に2、3個生産するペースだった。だが質の良さが評判となり、徐々に顧客が増え、売り上げも伸びていく。一番の懸念材料であった資金繰りについても、地元の金融機関の担当者のはたらきで、国民金融公庫から多額の融資を受けることができた。
 切粉
切粉高度成長期は過ぎていたが、切粉(きりこ)を出していれば確実に売り上げが出た時代だった。以降は右肩上がりに業績は伸び、独立5年目の1980(昭和55)年5月、法人化を果たすことができた。
ちょうどこの年は、70年代の2度の石油危機を乗りきった日本が、自動車生産台数において、アメリカを抜いて世界第一位に躍り出た年である。藤井金型も場所こそ同じ江南工場での間借であったものの、スペースは拡張し、機械も人も増えた。事業は順調に発展していくようにみえた。